(1)地下水を浸透、貯留する大きな水がめ(地下水盆)の存在
行政的には、熊本市、合志市、大津町等11市町村の範囲(1,000k平方メートル)
(2)地下水を浸透、貯留させる地層の存在
阿蘇火砕流堆積物、砥川溶岩、砂礫層、新期火山灰等
(3)豊富な降水量
阿蘇山周辺は全国有数の多雨地帯
(4)地下水盆の存在
阿蘇カルデラ西側外輪山の山麓台地※から熊本平野の地下は、難透水性の基盤岩が深い。
→広くて深い盆地状の地下構造
※菊池、益城、植木等の台地部
ランドサット衛星写真
周辺山地と異なる色調
→異なる植生、土地利用
水系図
周辺に比べ、河川の発達が悪い
→雨水は台地上に溜まり、地下浸透しやすい
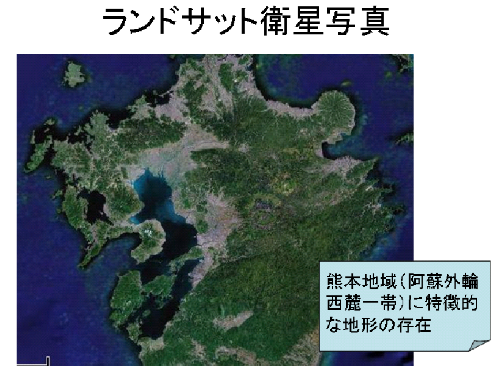
熊本・阿蘇周辺の水系
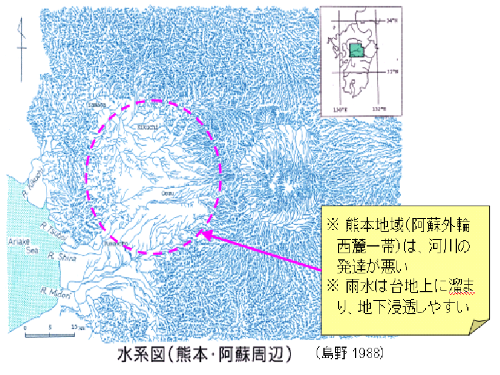
(5)地下水の浸透・貯留能力の高い地層の存在
(1)阿蘇火砕流堆積物
阿蘇カルデラの形成前に、計4回の大噴火(今からおよそ27万年前から9万年前)
このとき噴出した大量の軽石や火山灰等が強く固結
(阿蘇火砕流堆積物(溶結凝灰岩やシラス状)として、中九州一帯に広く分布)
菊池台地の地下にも厚く堆積
この火砕流堆積物の亀裂(クラック)部に大量の地下水を貯留
阿蘇火砕流堆積物の分布
菊池台地遠望
(2)砥川溶岩
益城町赤井火山から噴出した溶岩
益城町南部から嘉島町(井寺・浮島)、熊本市東部(健軍・江津湖)の地下に分布
溶岩の上部は亀裂が発達し、地下水を大量に貯留しやすい性質
熊本市上下水道局健軍水源地
5号井(深度40.5m)は、1本の井戸で日量1.4万m3の自噴量
砥川溶岩写真
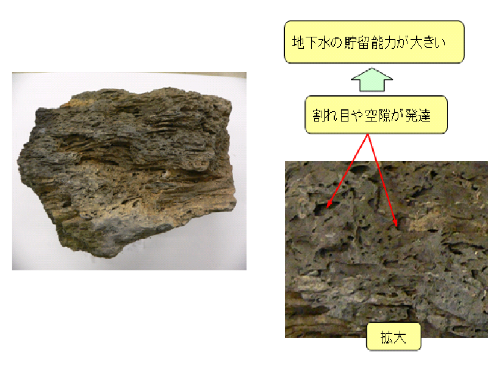
砥川溶岩分布図
(3)砂礫層
菊池台地、託麻台地等の段丘の地下に分布
(菊池砂礫層、託麻砂礫層等)
浅層の自由面地下水(第一帯水層)が存在
熊本平野の地下等では、浅層の島原海湾層、深層の未区分洪積層として帯水層を形成
(4)阿蘇火山新期火山灰土
阿蘇火山の中央火口丘から噴出した火山灰土
熊本では、赤ボク、黒ボクと呼ばれている
(黒ボクは、火山灰土に植物の腐植を多く含む)
阿蘇火山の周辺の表層を広く、厚く覆っている
未固結~弱固結で網目状の小さなひび割れが発達し、雨水の地下浸透を助けている
熊本地域の模式地質断面図
(3)豊富な降水量
阿蘇山周辺は全国的にも年間降水量の多いところ
阿蘇山上 3,206.2ミリ/年 (1981~2010平年値)
阿蘇谷 2,831.6ミリ/年
外輪山麓の台地部、平野部でも全国平均 (1,690ミリ/年)(国交省試算1976~2005)より多い降水量
菊池台地 約2,200ミリ/年
熊本市 1,985.8ミリ/年
東京 1,528.8ミリ/年(世界平均 約810ミリ)
↓
この豊富な降水量が、熊本地域の地下水の源
年間降水量の多少が、地下水位(湧水量)変化に大きく影響